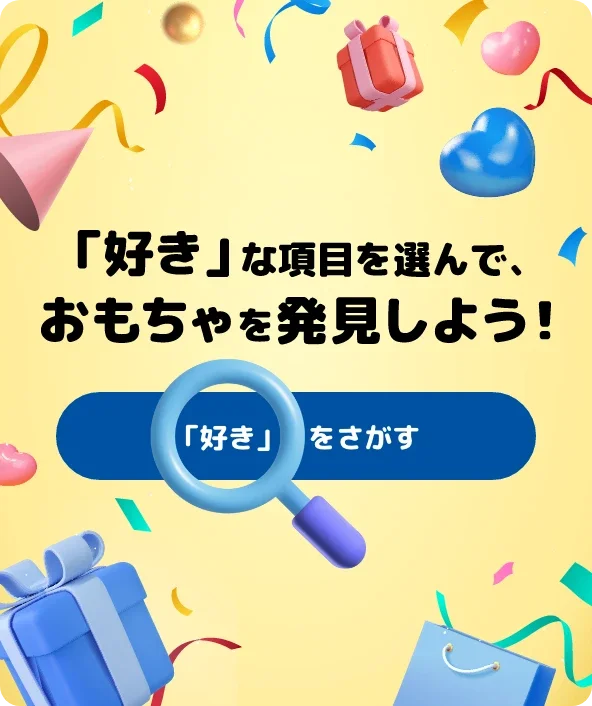project story 01
世界の共通言語になる日まで。
ぷにるんず️ デビュー戦略
本体の穴の奥にある「ぷにぷにボタン」を操作して、液晶の中のキャラクターを直接触っているかのような感覚が味わえる、
新触感液晶お世話トイ「ぷにるんず」。デビューからわずか3年でアジアを含む累計出荷数は90万個を超え、
早くも3作目を数える大ヒットシリーズはどのようにデビューし、急成長できたのだろうか。



H.N.
2021年入社
Hitsビジネス本部
ファッションエンターテイメント事業部
マーケティング課
研修期間を経て、ファッションエンターテイメント事業部に所属。現在は、ぷにるんずとクラフトホビー全般のマーケティングを担当する。

M.T.
2006年入社
Hitsビジネス本部
ファッションエンターテイメント事業部
マーケティング課
タカラとトミーが合併した2006年に入社。マーケティング部門に配属され、現在は、ぷにるんずを含むファッションエンターテイメント事業のマーケティングを管轄する。

Y.O.
2009年入社
Hitsビジネス本部
リカちゃん事業部
企画開発課
マーケティング部門に5年ほど在籍した後、商品開発部門でさまざまなキャラクター商品を担当。現在は商品企画立案を専門に行う。

デジタルにさわる、という愛着。
商品企画がスタートしたのは2018年。液晶とペットというテーマだけは決まっていた。そこから時代に合わせてどんな特長があればいいのかという考えを一つずつ加えていって、市場が求めている商品に仕立てていった。発売は2021年7月。ちょうどH.N.さんが入社して間もないタイミングだった。






検証の数が多いほど、最高の商品に近づける。
アイデアを商品として実現する。そのプロセスに待っているのは、検証に次ぐ検証だ。色、形、仕様、感触、動き。小さな玩具の中にあるあらゆる要素にとっての理想を、一つひとつ検証する。検証を重ねて辿り着いた理想形の集合体こそが、世の中がまだ知らない最高のアソビになる。



知りたい気持ちを呼び覚ますために外したセオリー。
一般的に、おもちゃは店頭にサンプルを置いて体験してもらうことで販売につなげるのがセオリーだ。しかし初代の発売時にはサンプルを置かないと決めてさわらせないようにした。実際に購入するまで、穴は見えるが、この中にいったい何がいるのかわからないからこそ、買ってさわってみたい。店頭に、そんな気持ちが生まれた。





オリジナル商品に対する疑問符を乗り越えて。
すでに世の中に認知のあるキャラクターを起用するよりも、オリジナルキャラクターをゼロから売り出すことは難しい。商品化決定会議では売上に結びつくかをシビアに判断する。それでも、いつも自部門の商品を一番におもしろがってくれるM.T.さんの声に後押しされ、オリジナルにこだわって発売した。いざ売れ始めると、懐疑的だった社内の声は吹き飛んだ。4年目にしてシリーズは第3弾へと進化し、キャラクターもどんどん増えていった。







おもちゃにとどまらず、新たなアソビの価値を創出し、世界中で愛されるIP※1へ成長させることが私たちのミッションですね。
※1:intellectual propertyの略称。「知的財産」と訳され、経済的な価値を有した情報の総称。一般的には人間の手で生み出された著作物の全般を指し、アニメ・マンガ・ゲームなどのキャラクターやロゴマークなどがIPに含まれる。

OTHERS